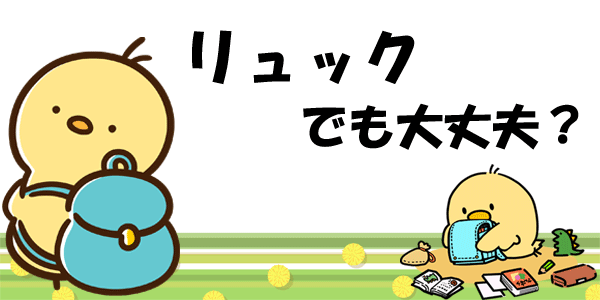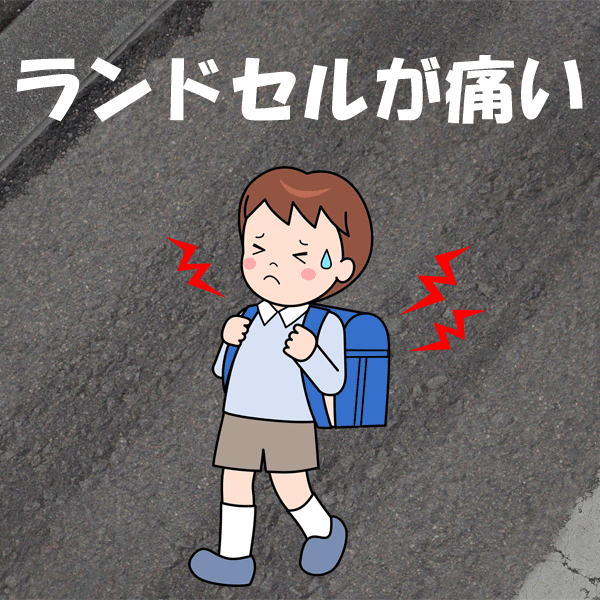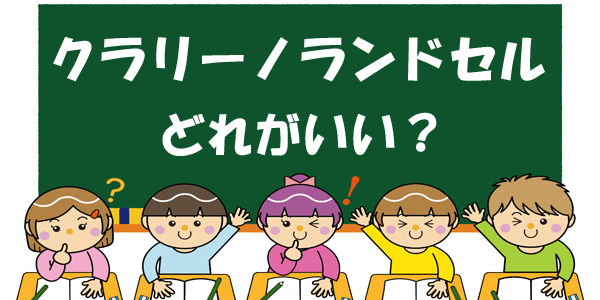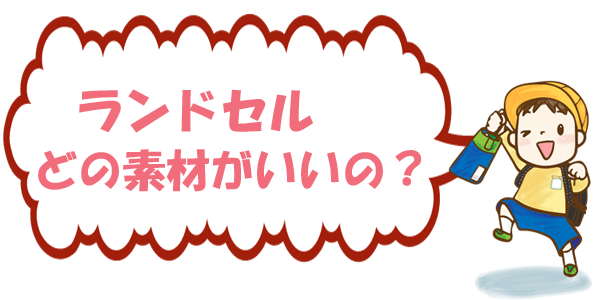軽い=背負いやすいではない!
「軽いだけ」ランドセルにご注意

[PR]
ランドセル症候群の誤解
ラン活を始めたママさんから、質問をいただきました。
テレビで「ランドセル症候群」を知り、ランドセルではなく、軽いナイロン製リュックを通学カバンにしたいです。おすすめはありますか?
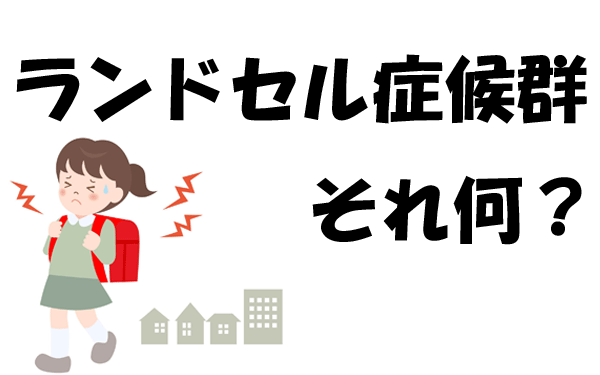
ランドセル症候群とは、重いランドセルを背負って通学する小学生が、体の不調を訴える症状。骨格形成に悪影響を与える懸念もあり、親としては気になる話題です。
- 肩こり
- 腰痛
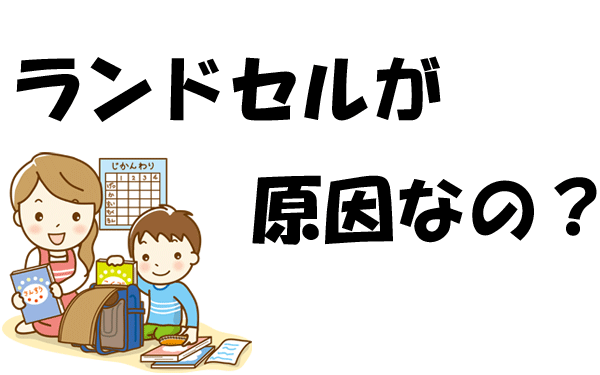
ランドセル症候群の原因は、ランドセルではありません。授業で使う学用品が、近年大幅に増えたことが原因です。
- 教科書ページ数が増加
※ 直近4年間で175.4%増量
※ 一般社団法人教科書協会(2021年調査) - 補助教材が増加
- タブレット端末の持ち帰り
文部科学省でも、この問題を認識して「児童生徒の携行品に係る配慮(通称:置き勉)」を促しました。ところがこの通達に対する先生達の反応はやや否定的。
- 紛失・盗難リスクが心配
- 机が重くなり掃除が大変
- 自宅で復習できない
- 保護者宛ての手紙も置いて帰る
- 準備習慣(忘れ物をなくす)がつかない
置き勉の進捗は、担任教師の考え方に委ねられてるのが実態です。
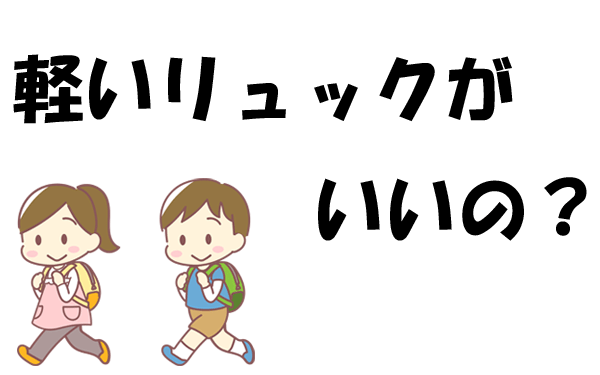
学習教材の増加は仕方ありません。それなら「軽いリュックを通学カバンにしよう!」と考えがち。ただそのアイデアはNGです。
| リュック | ランドセル | |
|---|---|---|
| 重量 |
1,000g以下 |
1,200~1,500g |
| 機能 |
低機能 |
高機能 |
| メリット |
軽くてかさばる荷物(体操着&給食袋)の持ち運びに最適 |
固くて重い荷物(教科書&水筒)でも体への負担が少ない |
| デメリット |
耐久性が低い |
リュックより重い |
「軽いリュックがいいかも?」と考えている親御さんは、物事の一面しか見えてません。
例えば、普段お買い物に使うエコバッグをイメージしてください。エコバッグに食材を詰め込み過ぎて、半端ない負担感を感じた経験はありませんか?

ナイロンやポリエステル製のエコバッグは、軽くて柔らかい。でも荷重分散&荷重軽減する機能はありません。だから食材の重みがダイレクトに伝わり、苦痛を感じます。
たとえ高価な登山用ザックでも、パッキングが下手だと本来の機能を発揮しません。小学生が教材の重量バランスを考慮して、荷物を詰め込むことは無理でしょう。
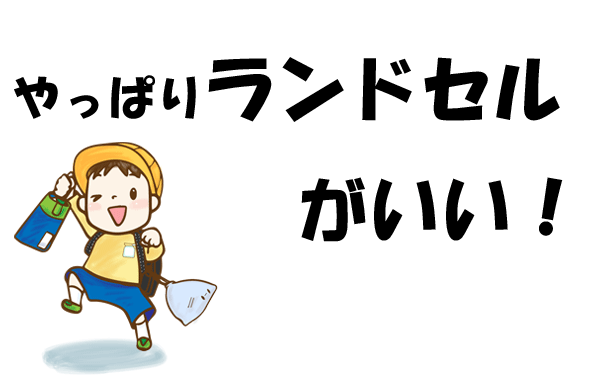
ランドセルは、子供の使用状況に合わせて、進化し続けている通学カバン。ドバっと荷物を詰め込んでも、最適なポジションで背負える工夫が随所にあります。
ランドセルを選ぶ時は「軽いランドセル」を探すのでなく、「軽く感じるランドセル(≒背負いやすい)」がおすすめです。
軽く感じるランドセルを紹介
セイバンの「スゴ軽 エアー」
【メーカー】セイバン
【モデル名】スゴ軽 エアーⅡ


当サイト調べでは、一番軽いランドセル(890g)。天使のはね基本機能はもちろん搭載。これをベースに、デザインが施されたラインアップもあります。
価格 |
¥62,700(税込)
|
|---|---|
重量 |
約890g |
主素材 |
クラリーノ® エフ「レインガード® Fα」 |
フィットちゃんの「ゼロランド」
【メーカー】フィットちゃん
【モデル名】ゼロランド (安ピカッ/楽ッション)


軽くて高機能な半カブセタイプのランドセル。クッション性のある肩ベルト(楽ッション)は、今までにない背負い心地を実現すると評判です。
価格 |
¥66,000(税込) |
|---|---|
重量 |
約1,050g |
主素材 |
クラリーノ® タフロック® NEO |
フィットちゃん最軽量は、楽ッションがつかない「ゼロランド(940g)」。
オーソドックスな「全かぶせ」から選ぶなら「軽量タイプ(1,050g)」。
フィットちゃんで購入するなら「楽ッション」搭載モデルがおすすめ。背負い心地で失敗することはないでしょう。
このさきの「basie(ベイシー)」
【メーカー】このさき
【モデル名】basie(ベイシー) クラリーノ


素材やパーツ強度を維持しながら、軽量化を実現したキューブ型。その代表モデルが、このさきのbasie(ベイシー)です。
価格 |
¥63,000(税込) |
|---|---|
重量 |
約1,100g |
主素材 |
クラリーノ® エフ |
水野鞄店の「ハネッセル」
【メーカー】水野鞄店
【モデル名】ハネッセル


肩ベルトの長さを38段階も調整できる「ラチェットアジャスター」を搭載。ワンタッチ機能だから、歩きながら子供が自分で微調整できるのがメリット。常にジャストフィットの背負い心地です。
価格 |
¥61,380(税込) |
|---|---|
重量 |
約1,190g |
主素材 |
コードレ タフガード® |
とことん背負い心地にこだわりを持つメーカー。ラチェットアジャスター以外にも、硬さが異なる3層のクッション材を利用して、肩ベルトの荷重分散を狙っています。
ハネッセルは資料請求で貰えるクーポンを利用すれば、全商品を5万円台で購入できるコスパに優れたメーカーです。
キッズアミの「ラビットワイド」
【メーカー】キッズアミ
【モデル名】ラビットワイド


ランドセルの重みを耐圧分散させる「ウィンディソフト」を搭載。クッションの厚みが増えると少し重くなりますが、背負い心地は向上します。
価格 |
¥61,600(税込) |
|---|---|
重量 |
約1,050g |
主素材 |
クラリーノ® エフ |
無駄なモノを削ぎ落した「かるかる」
【メーカー】神田屋鞄製作所
【モデル名】かるかる


神田屋鞄で一番安くて軽いランドセル(980g)です。補強材は他シリーズと同じ物を利用しているので、丈夫で長持ちするランドセルです。
価格 |
¥53,000(税込)
|
|---|---|
重量 |
約980g |
主素材 |
クラリーノ®エフ |
神田屋鞄は軽くて丈夫なランドセルを作ります。もう少しデザインの幅を持たせた「カルちゃんランドセル」や、自由にカスタマイズする「オーダーメイド」にも対応している工房です。
牛革でも軽い「たくみライトモデル」
【メーカー】モギカバン
【モデル名】たくみライトモデル


かぶせは「牛革スムース」で高級感をもたせる一方、本体はクラリーノで軽量化。
カラーに合わせて「ソフトゴールド」や「アンティークゴールド」の金具を使い分け、エレガントな仕上がりになってます。
価格 |
¥70,000 / ¥73,000(税込) |
|---|---|
重量 |
約1,200g |
主素材 |
牛革&クラリーノ |
もともとモギのランドセルは「大容量にもかかわらず軽量」との評判でした。
それをさらに進化させたモデルは、「軽さ」に加えて「牛革の質感」を求める人におすすめです。
Rikomonの「リュッセル」
【メーカー】Rikomon(タカアキ)
【モデル名】リュッセル NINE(ナイン)


カブセと肩ベルトが人工皮革だから、見た目はシンプルなランドセル。でも本体に「ナイロン中空糸生地(糸の中が空洞)」を使うことで、軽さを実現したランドセル型リュック。
価格 |
¥55,000(税込) |
|---|---|
重量 |
約999g |
主素材 |
|
リュッセルの最軽量は、エントリーモデルの「リュッセル FLY(900g)」。
ただ、サイドポケットに水筒が入り、タブレット専用ポケットまである「リュッセル NINE」のほうが、入学後の満足度は高いと思われます。
お得感がある「かるすぽエール」
【メーカー】イオン
【モデル名】かるすぽエール


イオンのかるすぽシリーズから、軽量化に重点を置いた商品が登場しました。セイバンとの共同開発なので、背負い心地に定評のある「天使のはね」が使われてます。
各社のランドセルが高額化している中で、5万円台という価格設定もお財布に優しい値段です。
価格 |
¥55,000(税込) |
|---|---|
重量 |
約1,080g |
主素材 |
アンジュエールグロス、パール |
イオンのランドセルは安っぽいイメージがありましたが、最近は機能とデザインを両立させたランドセルが増えてます。それでいてコストは抑えられているので、入学後の満足度が高いブランドになりつつあります。
背負い心地を左右するポイント
① 強度設計
- 耐久性(型崩れ防止)
ランドセルの型崩れは、背負い心地に影響します。小学生の肩こり・腰痛問題は、「ランドセルの重さ」より「ランドセルの型崩れ」と関係が深い。
チェック方法
一番型崩れしやすい「大マチ上部の開口部」に、変形を防止する補強材(樹脂)があるとベスト。ランドセルの大マチ開口部へ力を加え、歪み具合や反発力を確認してみるといいです。
- 収容力の罠
昨今は、どのメーカーでも「軽い・大きい」をアピールしてます。ここで避けるべきは「耐久性」を犠牲にして「収容力」をアップさせたランドセル。このパターンは最悪。ランドセルに入る量が増える分だけ、早期に型崩れが発生します。
チェック方法
カタログで内部構造を丁寧に解説している良心的なメーカーを選びましょう。「耐荷重試験」や「押圧試験」の結果データを、公表しているメーカーなら安心です。
② 肩ベルト

- 肩ベルトの立ち上がり
肩ベルトが立体的に立ち上がっているほうが、子供の肩にフィットしやすいです。 入学当初は浮きがあっても、荷物が重くなる頃には肩に馴染んできます。 - 肩ベルトの形状
体力がない低学年は、子供の胴体に寄り添うS型・X型の形状が最適。ランドセルの横ブレを防ぎます。
ただ高学年になると、ストレート型のほうが自然に背負えます。成長に応じてベストな形状が変わるので、あまり神経質になる必要はありません。
③ 背カン
背カンは、ランドセル「本体」と「肩ベルト」を繋ぐ重要パーツ。
【背カンの動き】
- 固定(動かない)
- 左右同時に動く
- 左右別々に動く
色々ありますが、背カンは動くタイプがおすすめ。背カンが動くことで、ランドセルを最適なポジション(背中の中心)へ誘導します。また着脱も楽になります。

④ 背あて
背あては、ランドセルと背中のクッション。人間工学に基づき、異素材を組み合わせたクッション材は快適です。
チェックポイント
- 素材
- 厚み(クッション性)
- 耐圧分散
- 通気性
【入学後】肩ベルト穴のこまめな調整
小学生は1年間で6cmも身長が伸びます。また冬服で厚着になると、ランドセルが窮屈に感じることもあります。
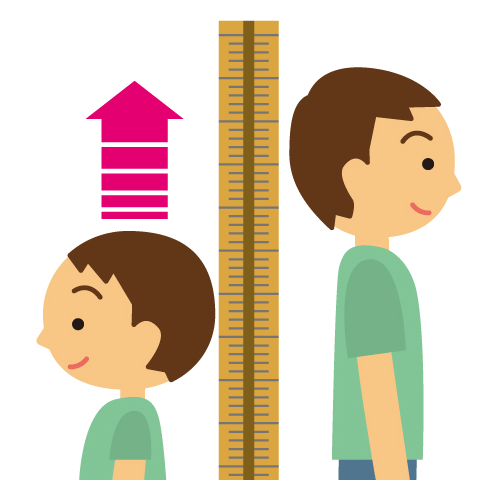
ランドセルの肩ベルトには、7~8個の穴(3~4cm間隔)があります。最低でも年に一度は、肩ベルトの穴を調整してあげましょう。
- ランドセルトップが肩と同じ高さ
(横から見る) - 背負ったランドセルが地面に垂直
(少し離れて見る) - 背中とランドセルに隙間が少ない
(手を入れてみる)
肩ベルトが短いと窮屈で動きずらい。長すぎると後ろ重心で猫背になりがちです。ベルト調整後、子供の姿勢を観察してあげてください。
ランドセル症候群(肩こり・腰痛)を防ぐには、肩ベルトの長さ調整が大事!
最新の機能的なランドセルは、肩ベルト調整さえ怠らなければ、自動的に体に寄り添い快適です。
ナイロン製リュックは、ランドセルより耐久性・機能性に劣ります。「軽い」という理由だけで選んでしまうと後悔する可能性もあるでしょう。
ランドセルを持ち運ぶキャリーケース(さんぽセル)などのアイデア商品も出てますが、ベルト調整で解決するのが基本的な考え方になります。